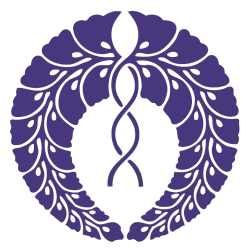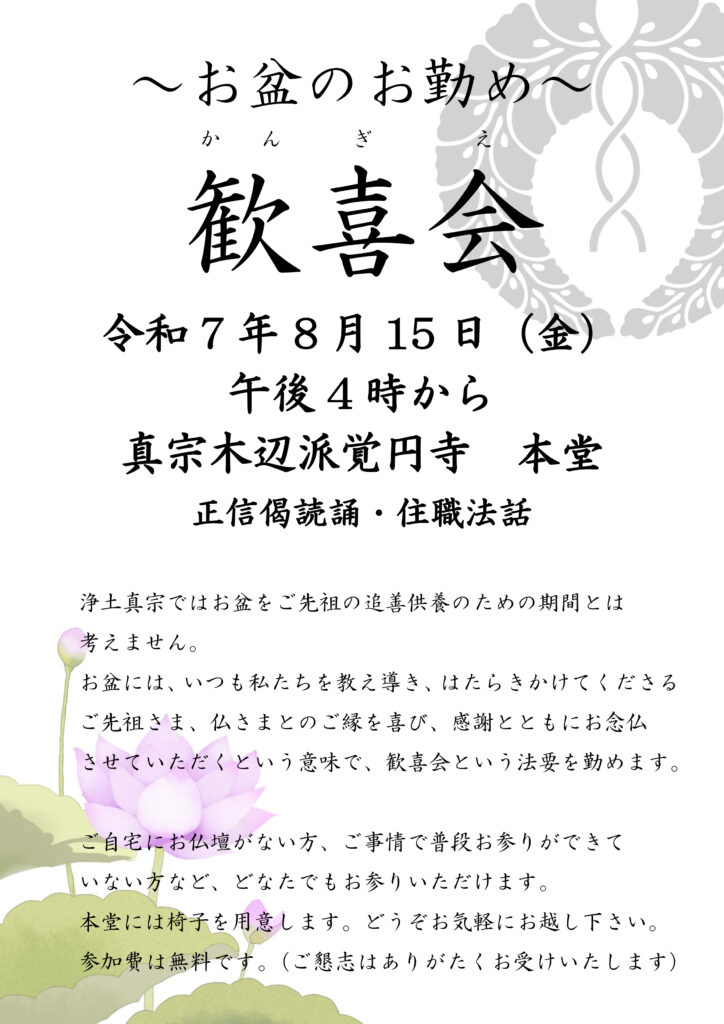
覚円寺では今年から、お盆の法要である「歓喜会(かんぎえ)」をお勤めすることになりました。
令和7年8月15日(金)
午後4時から
本堂にて
浄土真宗では、ご先祖さまは阿弥陀さまのおはたらきによって、すでに浄土に往生し、仏さまとなられ、いつでも私たちを導いてくださっていると考えます。
お盆の期間中だけこの世に還ってこられるんだという発想はありません。
そのため浄土真宗の寺院では、他の多くの宗派で行われている迎え火や送り火、施餓鬼、精霊流しといった儀式を行うことはありません。
お盆には、常に私たちに向かってはたらいてくださっているご先祖さま、仏さまのご縁を喜び、あらためて感謝させていただくための法要として、浄土真宗では「歓喜会」をお勤めするのです。
ご自宅にお仏壇があるご家庭には、住職がお伺いしてお勤めすることもできますが、お仏壇がない、あるいはなんらかのご事情でお参りができない方もおられることでしょう。
ご先祖さま、仏さまとのつながりを感じることができる、お盆というとても尊いご縁に、ともにお念仏できる機会となれば、と考えています。
どうぞ覚円寺の本堂にお参りください。
事前のお申込みは不要です。
本堂内は椅子を準備しておりますので、正座が心配という方も大丈夫です。
またエアコンも完備しておりますので、快適にお参りいただけることかと思います。
ただ、今年は毎日猛暑が続いております。道中は熱中症対策をしっかりなさって、お気をつけてお越し下さい。